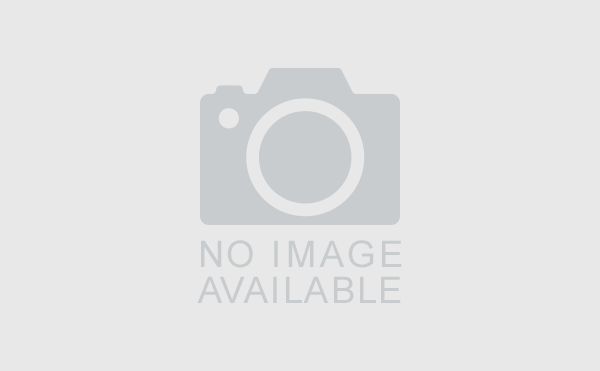2016.9.10 北本自然公園
夜鳴く虫研修
□日時 2016年9月10日 15時15分〜16時45分 座学 18時〜19時30分観察
□講師 埼玉県自然学習センター 高野徹さん
□場所 埼玉県自然学習センター及び北本自然公園
早めに着いたので、館内見学。学習センターの掲示板は充実していて勉強になる。
最初の15分間、ヘビのレクチャーがあり、ヘビの特徴を学んだ。ヘビは足がなく、まぶたは透明(ヘビの抜け殻に透明な幕がありびっくり)舌は臭いを吸着する器官(ヤコブソン)、毛はなくうろこ、外耳はなく、内耳のみ。シマヘビは触っても大丈夫である。
15時30分〜16時45分「夜の鳴く虫 コオロギ キリギリス」座学
たくさんの虫が鳴いているときは、耳に手をあてると聞きやすい。場所によって棲んでいる虫が違う。環境との結びつきが強いものを指標種という。
○公園やゴルフ場
シバスズ(小さなコオロギ) マダラスズ ホシササキリ(キリギリスの仲間)
○農耕地や道ばた
ミカドコオロギ エンマコオロギ ハラオカメコオロギ ウスイロササキリ コバネヒメギス ツツレサセコオロギ コバネヒメギス
○河川敷や砂地
マツムシ スズムシ ハマスズ(6〜7㎜)
○クズ、カナムグラなどのマント群落
カンタン(2000ヘルツ大きさ2㎝人間に心地よく聞こえる)ヒガシキリギリス(昼間なく)ハネナガキリギリス(北海道)クツワムシ(マメ科の植物を食べる)クサキリ ハタケノウマオイ(スイッチョン)
○湿性ヨシハラ
キンヒバリ(5〜8月に鳴く 幼虫越冬)ヤチスズ クマコオロギ(足がオレンジ) ヒメコオロギ ヒメギス(昼間鳴く)コバネササキリ イズササキリ(3段階で飛ぶ、撮影しにくい 8.9月昼間鳴く)カスミササキリ オオクサキリ
○林縁の草地やササヤブ
クサキリ ハヤシクサキリ セスジツユムシ エゾツユムシ(初夏から夏) サトクダマモドキ ヘリグロツユムシ クサヒバリ(樹上で鳴く) ヒゲシロスズ モリオカメコオロギ ヒサゴクサキリ(笹藪にいる。背中の模様がひょうたん型 顔に緑色の隈取り)
○林の中
ヤブキリ(肉食性) コロギス(葉をたたいて音を出す)ハネナシコロギス ヒメツユムシ(ササキリモドキ)クロスジコバネササキリモドキ カネタタキ(常緑の木にいる)ウスグモスズ(外来種)アオマツムシ(外来種)
1ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科 ♂成体 (新井氏同定)

2スグロオニグモ コガネグモ科 (成体か幼体か不明)(新井氏同定)

3ヤマシロオニグモ コガネグモ科 (成体か幼体か不明)(新井氏同定)

4キンミズヒキ バラ科

5クサギの花ももう終わり

6ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科 幼体 (新井氏同定)

7ハギ 駐車場に咲いていた種類が分からない

8シロカネグモ属の一種 (成体か幼体か不明)オオシロカネグモ♀成体の可能性もアリ(新井氏同定)

9ママコノシリヌグイ

10ヒメウラナミジャノメ

11アオマツムシ

12ササキリ♂

13コガタコガネグモ コガネグモ科(成体か幼体か不明)♀成体の可能性あり(新井氏同定)

14ユウマダラエダシャク

15オジロアシナガゾウムシ

16アブラゼミ

17ショウリョウバッタ

18ツチイナゴ幼虫

19ササキリ♂

20ワカバグモ カニグモ科 幼体

21クワキヨコバイ

22シロヒトリ

23シブイロカヤキリ

24クビキリギス

25-1ヒサゴクサキリ

25-2ヒサゴクサキリ

25-3ヒサゴクサキリ

26コゲチャオニグモ コガネグモ科 (成体か幼体か不明) かもしくは、「ヤマシロオニグモ」でもこういう色彩斑紋もあり(新井氏同定)

27-1クツワムシ

27-2クツワムシ

28ツツレサセコオロギ

29マメイタイセキグモ ナゲナワグモ科 ♀成体・卵のう (新井氏同定)

30-1オオトリノフンダマシ ナゲナワグモ科 ♀成体 (新井氏同定)

30-2オオトリノフンダマシ卵のう

31コバネササキリ

32-1コバネササキリ

32-2コバネササキリ

32-3コバネササキリ

33ハサミムシ 外来種

34クビキリギス幼虫

35ホシウスバカゲロウ

36ヤマトゴキブリ

37マダラカマドウマ